マヤ文字 目次 概要 ランダのアルファベットから生じた誤解 脚注 参考文献 関連書籍 関連項目 案内メニューマヤ文字編歴
アステカ文字絵文字ペルシア文字ウルドゥー文字オスマン語の文字ジャウィ文字マグレブ文字
表語文字Unicodeに存在しない文字音節文字象形文字マヤ文字メソアメリカ文明マヤマヤ語族
英西2世紀マヤ地域象形文字石碑絵文書表意文字音節文字ソビエト連邦ロシアユーリー・B・クノーロゾフ石碑ハインリヒ・ベルリン紋章文字タチヤナ・プロスクリャコーワピエドラス・ネグラスディエゴ・デ・ランダロゼッタ・ストーン音節文字ユーリー・クノーロゾフエリック・トンプソンマイケル・D・コウデービッド・H・ケリー
マヤ文字
ナビゲーションに移動
検索に移動
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年12月) |
| マヤ文字 | |
|---|---|
 漆喰に刻まれたマヤ文字(パレンケ博物館蔵) | |
| 類型: | 表語文字 (表語文字と音節文字の混用) |
| 言語: | マヤ語 |
| 時期: | 紀元前3世紀頃-紀元後16世紀 |
Unicode範囲: | 割り当てなし |
ISO 15924 コード: | Maya |
注意: このページはUnicodeで書かれた国際音声記号 (IPA) を含む場合があります。 | |

マヤ文字の表記の例。表語文字として一字で意味を表す場合と音節文字を組み合わせて読みのみを表す場合の例。そのほかわざわざ表語文字に音節文字を組み合わせる場合がある。

トロ=コルテシアヌスの絵文書。神々の儀式や暦の記述等が主であるが、よく観察すると神々の上の段に記述された文字がVOSの順に並んでいることがわかる。
マヤ文字(マヤもじ。英: Mayan Glyph, 西: Escritura Maya)は、主として紀元2世紀頃からマヤ地域で使用された一種の象形文字である。
目次
1 概要
2 ランダのアルファベットから生じた誤解
3 脚注
3.1 注釈
3.2 出典
4 参考文献
5 関連書籍
6 関連項目
概要
石碑や絵文書に描かれた1マス分の文字のなかの、主要な大きな部分を「主字」と呼び、小さな部分を「接字」と呼ぶ。
同じ意味、同じ発音の言葉でも、特定の一図形で単語を表す(表意文字)場合と、音節文字の組み合わせでひとつの単語を表す場合とがある。つまり「盾(パカル)」を盾の象形文字1字で表現したり「ぱ(pa)」「か(ka)」「ら(la)」という三つの音節文字の結合形で表現したりする。これは、同じ文脈の中で両方を混用するケースもあることから、日本語における漢字とひらがなの関係、さらには漢字のふりがなのような関係で、表意文字と音節文字が並存しているとみることができる。主に、神様や暦、都市国家の紋章などが単独図形による文字として使われている。
こうした法則は、当時のソビエト連邦(のちロシア)の研究者ユーリー・B・クノーロゾフによって発見され、1952年に発表された。
また、石碑に刻まれたマヤ文字は、歴史を記していることが、ハインリヒ・ベルリンによるいわゆる「紋章文字」の発見(1958年)と、タチヤナ・プロスクリャコーワによるピエドラス・ネグラスの碑文の解読(1960年)によって証明され、現在ではある程度の王朝史までが再構成されている。 文字には以下の種類がある。
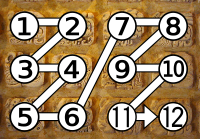
マヤ文字の読み順の例
- 幾何体(きかたい)
- 幾何的な文様の文字。部分的に頭字体の要素に含まれるケースもある。
- 頭字体(とうじたい)
- 人や動物の頭をかたどった文字。幾何体に似た部分(弁別要素)を持っていたり、幾何体の一部が含まれたり、幾何体を頭の形に変化させたものがある。
- 全身体(ぜんしんたい)
- 主に人物や動物の神を組み合わせたような全身像を描いた文字。主に暦の文字に用いられた。文字の読み方は、たいていは縦2行一組で「左→右→(下へ)左→右」と読まれる。この読み方の起源は、暦の導入文字が2行分とっていて、その下に文字を2列に刻んだことから始まったと推定されている。
ランダのアルファベットから生じた誤解

マヤ文字 ディエゴ・デ・ランダ司教の『ユカタン事物記』(16世紀)の「ランダのアルファベット」のページ。ランダはマヤ文字の記された文章を大量に焼却したが、布教活動などに役立てるため研究を続けた

ランダが伝えたスペイン語のアルファベットの呼び名をナチ・ココムが忠実に描いたため、水を表すhaが[atʃe(アチェ)+a(ア)]になり、「わな」を表すléが[ele(エレ)+e(エ)]として記録されることになってしまった。
「ランダのアルファベット」とは、ディエゴ・デ・ランダがスペイン語のアルファベットにあわせ、情報提供者であったマヤ貴族出身のナチ・ココム[注釈 1]にマヤ文字を書かせてできあがった、マヤ文字のリストである。
子音のみの場合とアルファベットの音をそのまま表記にした場合とで異なるために、後世のマヤ文字研究に混乱と障害をもたらし、でっち上げ説まであらわれた。しかし反面、しばしばマヤのロゼッタ・ストーンとも評されるように、幸運にも音節文字の記録が残ったために解読の重要な手がかりであったことが、ユーリー・クノーロゾフによって明らかにされた。しかし、当時の西側のマヤ研究を主導していたエリック・トンプソンはクノーロゾフの説を認めず、批判を繰り返した。当時のアメリカの研究者はトンプソンの強い影響下にあったため、トンプソンの生前にクノーロゾフの説に賛成したのは、マイケル・D・コウやデービッド・H・ケリーなど少数だった[1]。
ランダがナチ・ココムに、スペイン語の文字に当てはまるのは何かと聞いたとき
- a(ア,[a])というと「亀」(ac)という字の頭の部分
- b(ベ,[be])というと「道路」を表すベ(be)の文字
- c(セ,[θe])というと「セック」(Zec,[sek])という月の名に当たる文字
を書いたという具合である。
そして、ランダがh(アチェ[at ʃe])といい、ユカテコ語で「水」を表す「ハ(ha)」について、h(アチェ[at ʃe])とa(ア)で表記するということから、ナチ・ココムは、ランダの指示にしたがって[a]+[tʃe]+[a]という音節文字を書くことになって、ランダはそれをahaと書くと解釈した。
また「わな」を表すレ(lé)ということばをどう書くかと聞いた場合、ナチ・ココムは、最初図下段で表した四番目の文字のように一文字で「レ」(lé)と書いたが、ランダは納得せず[注釈 2]レ(lé)はエレ(l[ele])とエ(e[e])で書き表すと説明し、再度書きなおすことを求め、ナチ・ココムは仕方なくエ[e]とエレ[le]とエ[e]に当たる文字を並べた。そして改めてランダは、エレとエでなる「わな」という字はどう書き表すのかたずねると、再び一文字で「レ」(lé)と書いたため、結局、[e]+[le]+[e]という文字と「レ(わな)」(lé)という表語文字が書かれることになった。つまりランダは、個々の文字をe,l,e,leと考えたが、実際には、eleeléと書かれることになった。
脚注
注釈
^ 洗礼名でドン・ファン・ココムと『ユカタン事物記』 (Relación de las Cosas de Yucatán) に記される。かってマヤパンを支配したココム家の末裔。ココム家は、ウシュマル近郊に住んでいたシウ家によって虐殺されたが、ココム家の一族でホンジュラスのウルワ川流域地方に商売に行っていたおかげで虐殺を免れた人物の4代目の子孫にあたる。[要出典]
^ ランダは、ヨーロッパ人独特のアルファベット以外の文字体系が存在することに対して、認識が及ばなかった。[要出典]
出典
^ Coe (1992) pp.152-160
参考文献
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2013年12月) |
- 青木晴夫『マヤ文明の謎』講談社〈講談社現代新書 757〉、1984年12月。.mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
ISBN 978-4-06-145757-7。 - ランダ, D「ユカタン事物記」『ヌエバ・エスパニャ報告書/ユカタン事物記』ソリタ著・小池佑二訳注/ランダ著・林屋永吉訳・増田義郎注、岩波書店〈大航海時代叢書 第2期 13〉、1982年7月。
ISBN 978-4-00-008533-5。
Coe, Michael D (1992). Breaking the Maya Code. New York: Thames and Hudson. (日本語訳:マイケル・D. コウ『マヤ文字解読』創元社、2003年)
関連書籍
- 八杉佳穂 『マヤ文字を解く』中央公論社〈中公新書 644〉、1982年3月。ISBN 978-4-12-100644-8
- 山瀬暢士 『マヤ文字入門』 太陽書房、2002年12月。ISBN 978-4-901351-40-9
関連項目
- 紋章文字
| ||||||||||||||||||||||
カテゴリ:
- 表語文字
- Unicodeに存在しない文字
- 音節文字
- 象形文字
- マヤ文字
- メソアメリカ文明
- マヤ
- マヤ語族
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.336","walltime":"0.505","ppvisitednodes":"value":4205,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":65486,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":15413,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":4,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":5749,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 396.046 1 -total"," 38.61% 152.919 3 Template:Cite_book"," 29.02% 114.946 2 Template:Cite_book/和書"," 22.57% 89.386 1 Template:出典の明記"," 18.67% 73.952 2 Template:ISBN2"," 18.37% 72.746 2 Template:Ambox"," 10.96% 43.393 2 Template:Catalog_lookup_link"," 7.35% 29.125 1 Template:Commonscat"," 6.83% 27.060 1 Template:Citation/core"," 6.59% 26.080 1 Template:Sister"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.042","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2121742,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1332","timestamp":"20190429182249","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u30deu30e4u6587u5b57","url":"https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A4%E6%96%87%E5%AD%97","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q211248","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q211248","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-06-12T14:46:24Z","dateModified":"2017-07-21T23:37:41Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Palenque_glyphs-edit1.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":114,"wgHostname":"mw1258"););